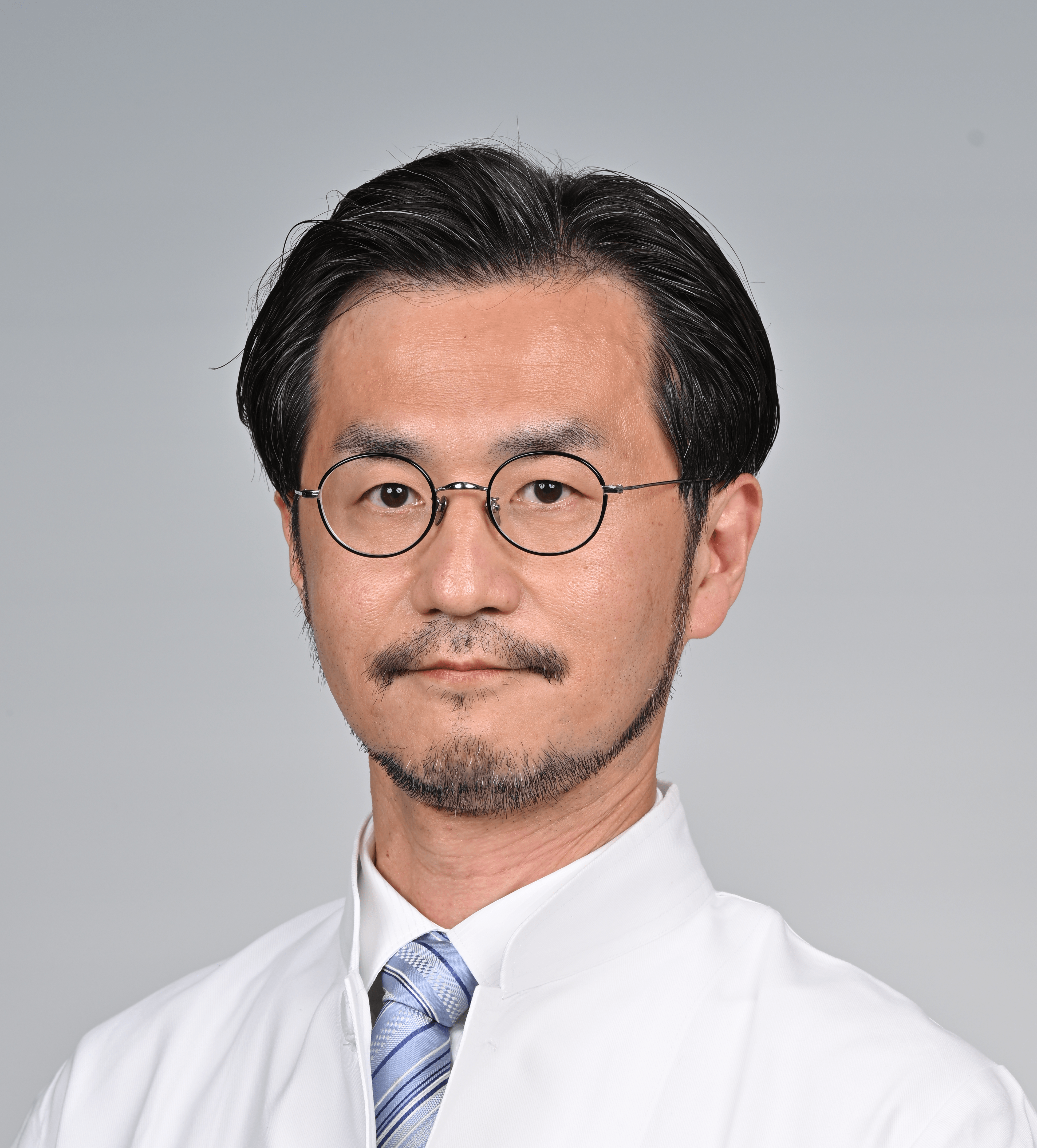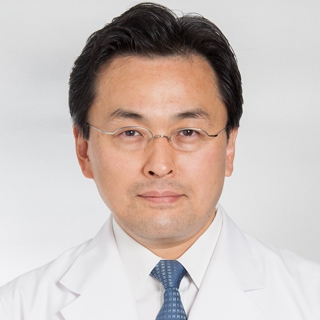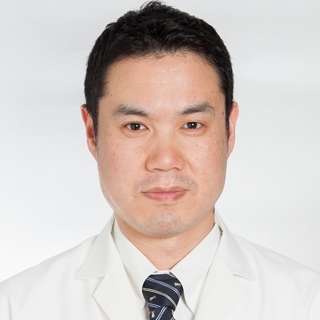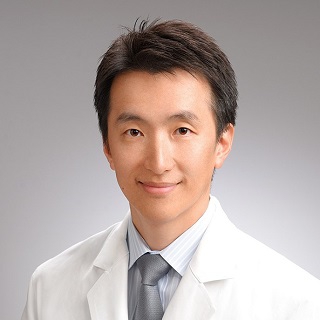概要
精神・神経科では、気分障害、統合失調症、うつ病、不安障害、認知症、脳器質疾患、てんかんをはじめとした精神・神経疾患の診断、治療を行っています。診断のため、血液検査・画像検査だけでなく、様々な心理検査・神経心理学的検査を受けることも可能です。
特色・方針・目標
私たち精神・神経科は脳とこころの問題を扱います。どのような経緯で心身の不調を生じるに至ったかを、脳とこころ、からだ、 環境などの視点から 統合的に理解していきます。
当科では、日本で屈指の長い歴史を誇り、精神症候学の伝統を重んじる一方で、さまざまな先進的な診断技術・高度精神医療を推進し、薬物療法・精神療法に加え、環境調整や社会的資源の積極的な活用を図っています。治療にあたっては、臨床各科とのリエゾン、コンサルテーション、患者さんが生活している地域、さらには専門施設との連携を行っています。
対象疾患は次のようになっております
- 気分障害(うつ病、双極性障害)
- 統合失調症
- 心身症・身体表現性障害・自律神経失調症
- 摂食障害(神経性無食欲症、拒食症、過食症)
- 睡眠障害(不眠症、過眠症、睡眠・覚醒リズム障害など)
-
身体疾患に伴う精神的問題
- てんかん
- 物質関連障害
-
思春期・青年期精神障害
-
老年期精神障害(認知症、せん妄など)
-
家庭・学校・職場のメンタルヘルス
-
頭部外傷後遺症
-
高次脳機能障害
-
脳器質疾患
-
適応障害
-
アルコール使用障害
次のような症状を扱っております
・気分が沈み、悲観的に考える
・無気力で、何をしても面白くない
・集中力がない
・物忘れが目立つ
・イライラして怒りっぽい
・漠然とした不安がいつも続いている
・不安で外出が怖く、乗り物に乗れない
・不安のあまりパニックになる
・戸締まりや火の始末を何度も確認せずにいられない
・汚れやウィルス・細菌などがひどく気になる
・物音や周囲の出来事にひどく過敏になる
・体は不調だが、病院の検査では異常がない
・拒食,過食
・不眠
・学校や職場にうまく馴染めない
・学校や職場、家庭などで強いストレスを感じている
検査内容のご案内
-
一般血液検査
-
脳波
-
心理検査
-
神経心理検査
-
CT
-
MRI
主な実績
精神・神経科の外来初診件数は、年間約720件(2023年度)、再診件数は、年間約36107件(2023年度)です。初診時の診断としては、うつ病などの気分症圏が最も多く、続いて不安障害やストレス関連障害といった神経障害圏が占めています。入院件数は年間150件程度です。また当院では、難治性のうつ病などに対して実施される修正型電気けいれん療法にも力を入れています。
| 名称 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診患者数(診断別) | 人 | 2023年 |
| 神経発達症群 | 118 | |
| 統合失調症または他の一次性精神症群 | 62 | |
| 気分症群(うつ病など) | 250 | |
| 不安または恐怖関連症群,ストレス関連症群 | 229 | |
| 食行動症または摂食症群 | 30 | |
| 物質使用症群または嗜癖行動症群 | 5 | |
| パーソナリティ症群など | 6 | |
| 神経認知障害群(認知症など) | 20 | |
| その他 | 2 | |
| 計 | 722 |
ご挨拶
現代は「脳とこころの時代」と言われています。精神神経疾患はからだの病気とともに5疾病に挙げられ、その治療と対応はますます重要性を増してきています。当科は初代の下田光造教授以来、日本で屈指の長い歴史を誇り、精神症候学の伝統を重んじる教室です。その一方で、MRI・PET・SPECT等の画像検査をはじめ、さまざまな先進的な高度精神医療を推進してきています。思春期から超高齢者までのあらゆるライフサイクルの脳とこころの問題に対応しています。
すべての身体科とのリエゾン・コンサルテーションはもとより、関連するストレス研究センター、メモリークリニック、緩和ケアセンターなどの院内諸部門、さらには日本最大の同窓会所属診療機関などと連携して、患者さんとご家族にとってより良い治療を目指しています。

受診について
- 当院では患者さんの待ち時間を短縮するため、予約制を導入しています。
- ご予約方法は一般の患者さんと医療関係の方で異なります