概要
救急科はさまざまな救急疾患・外傷の診療を行い地域医療に貢献すると共に、卒前・卒後医学教育と研究活動を通じて、救急医療の向上に努めています。当院における救急車搬入数は、年間約7,500件と国内有数です。地域の健康危機に積極的に関与して社会に貢献しています。
特色・方針・目標
慶應義塾大学病院では救急車で搬入される患者の診療を救急科が受け持っています。救急車で搬入される患者は軽症から救命救急センターが対応するような重症まで、重症度に関わらずに救急科が診療を始めます。救急医学の専門医は、急病や外傷を臓器に関わらずに診療します。このため、救急科が救急患者の診療を開始することで、安全で質の高い救急診療ができます。そして、救急科での診療後、専門治療が必要と判断されれば、院内の専門医と連携して早期に専門治療を開始します。一方、救急科は重症患者の診療も得意にしており、多発外傷や重症患者の入院治療も救急科で行っています。また、災害時には、救急医学の知識と経験がとても役立ちますので、救急科医がリーダーシップをとっています。このように、救急科は救急医学という社会性・公共性の高い医学を専門とする医師が社会に貢献することを目標に文字通り、24時間365日の体制で診療にあたっています。
対象疾患は次のようになっております
-
上気道閉塞
-
意識障害
-
頭痛
-
めまい
-
胸背部痛
-
不整脈
-
呼吸困難
-
喀血
-
腹痛
-
消化管異物
-
尿路結石
-
尿閉
-
発熱
-
脱水
-
電解質異常
-
高血圧緊急症
-
糖尿病性昏睡
-
低血糖症
-
甲状腺機能異常症
-
急性副腎皮質不全
-
痛風
-
軟部組織感染症
-
鼻出血
-
頭部外傷
-
胸部外傷
-
脊椎脊髄外傷
-
四肢外傷
-
骨折
-
脱臼
-
血管損傷
-
電撃傷
-
化学損傷
-
一酸化中毒
-
食中毒
-
低体温症
-
溺水
次のような症状を扱っております
救急診療が必要な全ての救急疾患、救急外傷に関連した症状に対応します。
検査内容のご案内
-
採血
-
レントゲン
-
超音波検査
-
CT
-
MRI
-
血管造影
-
培養検査
主な実績
| 名称 | 件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 救急車搬入件数 | 7,550件 (3次救急 162件) | 2023年 |
| 救急車応需率 | 2次63% 3次42% | 2023年 |
| 入院患者 | 367件 (非外傷 229件, 頭部外傷 71件, 体幹部外傷 26件, 骨盤四肢外傷 41件) | 2023年 |
| 手術 | 103件 (体幹部47件, 骨盤四肢 46件、他 10件) | 2023年 |
ご挨拶
救急医療は、安全な社会生活を守るために欠かせない「セーフティー・ネット」の一部です。救急科は救急医療に関する病院の窓口であり、救急車で搬送されるほとんどの患者さんの診療を担当します。救急外来には24時間体制で救急科専門医が常駐し、重症度や年齢に関わらず、病気や外傷・熱傷・中毒などまで幅広く救命医療を含めて診療を行える体制が整えられています。診療の結果、各診療科の専門治療が必要な場合には、迅速に各診療科の医師と協力して治療を行います。入院を必要とする場合には、救急科を含め、病気の種類に応じた専門治療を考慮した適切な診療科に入院します。自力で救急外来を受診した患者さんには、看護師がトリアージを行い、各診療科の医師が中心になり対応します。また,当院は東京都災害拠点病院の一つに指定され、日本DMAT(Disaster Medical Assistance Team: 災害派遣医療チーム)指定医療機関にもなっています。
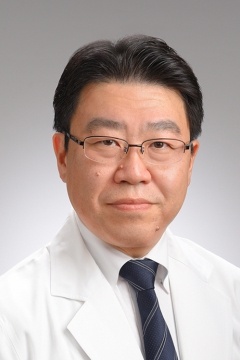
災害医療対応
当院は東京都災害拠点病院に指定されています。救急・災害医療の知識を持つ専門医療チーム(DMAT:Disaster Medical Assistance Team)も設置されています。
受診について
- 当院では患者さんの待ち時間を短縮するため、予約制を導入しています。
- ご予約方法は一般の患者さんと医療関係の方で異なります




